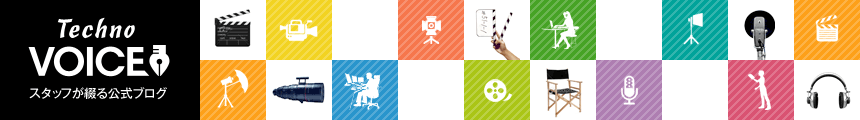【映像・広告】映像に関わり続けて-----アナログからデジタルへ------
2013年11月14日 10:40
現像所の朝は早い。
まずボイラーに火が入り、現像液の温度調整が行われる。
それまで微かな光の浸入も許さない丸いアルミ管に閉じ込められていた撮影済のフイルムは封印を解かれ、工場の工程に沿って一定の速度で流れていく。
それらがネガ像として現れるのは昼の光が差し掛かる頃になる。
このネガを反転させたポジ像のラッシュが上がり、都内に散在している制作プロダクションに運ばれるのは夕方近くになる。
この文章は小説「つなぎ屋」第八章の冒頭の一説です。
この小説はアナログ時代の全盛期とも言えるフイルム編集の現場を書いたものです。フイルムで撮影し、編集し、プリントを上げていた、いわばフイルムでの一気通関で映像作品を創っていた時代です。フイルム編集機はムビオラ、ステインベックを使用して、カット選び、編集点を探し、それをテープスプライサー(ギロチン)で"切った""張った"を繰り返し、まるで任侠道の世界のようでした。ただ、そこには手触り感覚でモノを作っていた感があり、苦しみ、悩みながら全身で創る喜びを感じていた時期でもありました。
仕事が終わったらどんなに遅くなろうが夜の街に出かけて行ったしんどくても楽しかった編集現場。
誰かがやってクライアントからダメ出しされた作品を自分の手で編集し直してOK
に漕ぎつけ、人知れず喝采を叫ぶ歪んだ快感。
編集の立場ながら撮影現場を演出する醍醐味。
これらを味わってまさしくアナログ時代を謳歌していた気がします。
それが、デジタル時代に突入し、今や、コンピュータ抜きでは映像が作れない時代になっています。映像編集機は素材をハードディスクに取り組んでさえすれば、カットの入れ替え、編集点の探り方などはアトランダムに瞬時にして行い、効率化、スピード化が進み、便利さが増し、手触り感覚がなくなってしまうようです。時には編集も会議室で行うなど、じっくり構えてモノ創りをする余裕がなくなった感すらあります。
さらにはコンピュータの申し子みたいなCGが多用され、映像表現技術の幅を広げているように見えます。ただ、ここに至っても映像創りはアナログ時代に築いたノウハウは大事であり、それを知らないでむやみに最新機器や技術に飛びついたりしてばかりいると、つねに何かを求めて糸の切れた凧のようにフワフワしていることになりかねません。
このように映像創りは、アナログからデジタルの世界へ入ろうが、コンピュータが指令を出して創られているわけではなく、それぞれの人による経験を元にした感性で競い合って創られています。
このことを実感するのは、皆が企画を出し合って完成させた作品を講評するときです。いつも初めに"講評は最高のクリエティブの場である"と切り出して始めることにしています。その際には、講師側の一方通行の話で終始するのではなく、双方向でキャッチボールすることが一番のポイントになります。
そこには、必ず人の生き様を反映したドラマがあり、それを追い求めた感性が生き生きと芽生えています。
"デジタルの究極はアナログである"
映像編集講師 本間 研二